
表題の“場”というのは、
広い意味では、
都道府県、地域で、
その他にも、
所属しているコミュニティを
指すこともあれば、
限定的な場所でもあります。
その“場”が人間に
及ぼす影響を悪も善も含めて、
分析して、
有効利用できるようになれば
素晴らしいとおもいませんか?
例えば、
まずはじめに、
大阪(わたしの出身地)
と
東京(今の居住地)について、
それぞれの地域(場)で
育った人達を観察していると、
明らかに特性に違いがあります。
大阪出身の私から
東京人を見ていると、
他人との付き合い方が
とてもスマート、
お互いに気を遣い合って、
なるべく浮かないように
大人しく会話し、
取り乱さず、
マウントせず
(していたとしてもそれを悟られないように)、
付かず離れずの一線を
引いたクレバーなつきあい方をしている、
と感じます。
東京には
地方(特に東北方面)から
出てきた人達の割合が
多いので、
自分の田舎者度合いを
悟られまいと、
まわりの様子を
見ながら浮かないように
合わせようと努力した
結果かも知れません。
エスカレーターは常時左立ち。
次に大阪人は、
“誰がオチを取るか”
“安く買った自慢大会”
“おもろい奴がかっこいい”
という考えを持っていて、
常に東京に対して、
根拠がわからない対抗心を
燃やしています。
エスカレーターは常時右立ち。
出身地(場)が
人間の思考・感情・行動に、
影響を及ぼしていますよね。
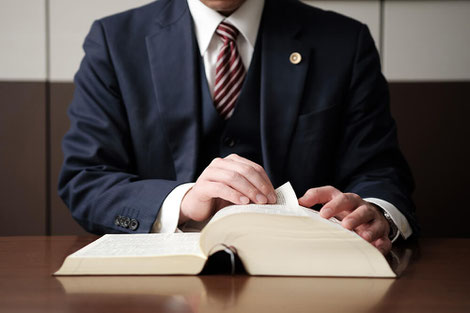
次の例示として、
業界・会社を観察してみます。
例えば、
国家公務員;永田町、霞が関に
務めている人、
ファッション・美容・理容業界に
務めている人、
医療業界に務めている人、
建築業界に務めている人
をよく観察してみると、
私服コーデ、身に着けている品物、
使っている言葉、
業界人が醸し出すオーラなど、
違いが認識できると思います。
それがいわゆる社風と
呼ばれるものです。
これは、
所属する業界(場)が
人間の思考・感情・行動に、
影響を及ぼしていますよね。
そして、
最後に、学校を観察してみます。
全国的に有名で対照的な
イメージを持った大学で、
いくつかピックアップしてみます。
早稲田大、慶応義塾大、明治大、
上智大、青山学院、
いわゆる校風のイメージが違うと
認識出来ると思います。
1880年後半から1900年代に
日本人が開学した歴史を持った大学
と
キリスト教宣教師の協力で開学した、
いわゆるミッション系大学でも
個々人の差異はあれど、
“〇×△大学と言えば・・・・”
一般大衆が持つイメージがあり、
それはそこに所属する
学生によって作られている訳です。
ですので、
これもまた所属する大学(場)が
人間の思考・感情・行動に、
影響を及ぼしています。

では、
なぜ人間は所属する場に影響を受けて、
その場が持っている空気感(集合意識)に
変化させていくのでしょうか?
それは、人間は社会性の動物で、
ある共同体を形成して、
お互いに補完し合って、
日常生活を営んでいます。
その共同体が形成される
物理的な空間、
または心理的なつながりの集合体を
“場”と呼んでいます。
この共同体(場)に
属し続けるためには、
必ず決められたルールを
守らなければなりません。
共同体メンバーが
相互に安心・安全を感じて、
“味方”だと認識して
もらうためです。
もし、ある共同体メンバーが、
自分勝手で、自己主張を強くして、
他人に犠牲を強いるような、
共同体メンバーが
安心・安全を感じられない
思考・感情・行動をしてしまうと、
異端児としてラベリングされて、
他の共同体メンバーから
距離を置かれたり、
冷たくされたり、
無視されたりして、
不安・恐怖心を煽られて、
ルールを守らないことが
どれだけ罪が重いか、
思い知らされ、
ルールを遵守するように
促されます。

それでも、
ルール破りが改善されなかった場合、
その共同体メンバーは、
異端児と呼ばれ続けて、
その共同体(場)から排除されます。
このルールシステムによって、
人間はその“場”に適応する
自分自身に変化していく訳です。
その変化した結果が、
上記でお示ししました、
県民性であったり、
社風や校風という訳です。
皆さんの身近にも、
何か問題意識があって、
それを解決したいと思っている
共同体(場)は、
会社だったり、
社会活動団体だったり、
政党だったり、
宗教団体だったり、
を見聞きするでしょうし、
ご自身も活動に
加わっているかもしれません。
ただ、この“場”が人を変える、
ルールシステムの弊害もあります。
それは、共同体(場)が
大切にしている、
思考・感情・行動以外を
受け入れられなくなることです。
今までに、
何度も成功体験をすることで、
思考・感情・行動がパターン化されて、
それに執着してしまい、
変化を怖れるようになります。
特に、独創性や創造性は、
共同体(場)が大切にしている、
思考・感情・行動の“外側”に
ありますので、執着を捨てて、
今まで大切にしてきた
“場”の外側に出ることが
絶対条件です。
民度が高い共同体にも、
低い共同体にも、
良し悪しがあり、
どちらを選択するかは、
あなたが決められます。
