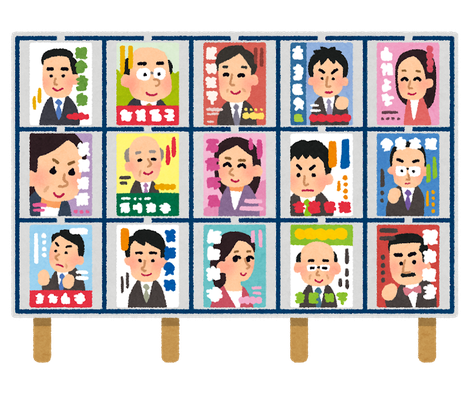
みなさんは表題の言葉を
聞いたことありますか?
表題の言葉は、
森永ヒ素ミルク
中毒事件
や
豊田商事事件
の被害者救済で
弁護団長として
活躍された
中坊公平さんの
言葉です。
人間が行動を起こす
理由が短い言葉に
よく表現されていると
思います。
私は
今回、
7月20日(日)に
投開票される
参議院選挙の選挙戦が
7月3日から
始まっているのですが、
各党候補者の演説を
聞いてみたり
選挙ポスターに
掲載されている
選挙公約を見てみると、
表題の言葉が
思いついたんです。
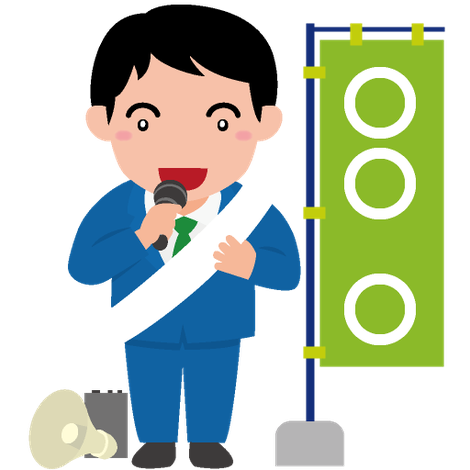
当たり前ですが、
各政党、
有権者の投票を
得て有権者との約束である
公約を果たすために、
議席を増やしたい、
そのためには、
今の他党に集まっている
注目を自分達に集めて、
投票してもらわなければ
ならない訳ですよね。
推しを変更して
もらう行動を
有権者に
起こしてもらうためには、
という視点で
表題の言葉を踏まえて、
演説とポスターを
チェックしてみました。
正面の理:
論理的に、
道理にかなった指示や
説明をすること。
物事の筋道を立てて、
納得できるように伝えること。
側面の情:
温かい言葉をかけたり、
世話を焼いたりするなど、
相手への思いやりを示すこと。
愛情を持って接することが、
信頼関係を築く上で大切
背面の恐怖:
恐怖を煽って、
言う通りにしないと、
怖い目に合う、
危機感を
現実に起こるものとして、
他人を、
集団を扇動して行動を
起こさせること

それでは、
正面の理
側面の情
背面の恐怖
のそれぞれが
どのように
使われているのか、
一部抜粋すると
正面の理:
"国民生活調査で
生活が
『苦しい』や『やや苦しい』と
感じている世帯は、
全世帯54.4%、
母子世帯86.7%、
25年の不況で
所得の中央値が
545万円から437万円に
約108万円下がっているから、
大胆な積極財政が必要"
この文言は
とても論理的で
理解しやすいものだと
思います。
側面の情:
『いままでに、こんなに勤勉で、
一生懸命に働いてきた
日本人の給料が
上がらないというのは、
おかしいと思いませんか?』
とか、
『異次元の少子化対策と
言いながら、
奨学金返済
大学卒業なら400万円
大学院卒なら1,000万円、
返済をしながら、
生活を立てて、
結婚して、
子供を育てる
余裕がありますか?』
など、人間の持っている
情動に訴えかける文言は
聞いたことあると思います
背面の恐怖:
『消費税を
減税・廃止してしまえば、
社会保障が出来なくなる』
とか、
『日本の借金が
大変なことになっています。
その額1,323兆円にのぼり、
消費税減税や
ガソリン暫定税率廃止は
出来ません』
など、
〇×がなくなると、
大変なことが起こるよ、
という論調で、
恐怖を煽る文言も
聞いたことがあると思います。

正面の理・
側面の情・
背面の恐怖、
どれにも良い所と
悪い所があります。
優性/劣性はありません。
使う際のバランスが
とても大切です。
ただ、
世の中が危機的状況で
あればあるほど、
側面の情が効果的です。
歴史上、
長期的に続いた体制
(ある特定の階層のみが
既得権益の恩恵を得られる)が
崩壊する際、
必ず革命を主導する
リーダーがいて、
そのリーダーの言葉は
大衆のココロに
寄り添った
名言になることが多いです。

例えば、
アメリカ:キング牧師が
公民権運動中に、
人種差別に苦しむ人々に
希望を誇りを与えた
“ I have a dream”
であるとか、
第二次世界大戦中に
首相となり、
危機にあった英国を勝利に
導いた
ウィンストン・チャーチルは、
” 凧が一番高く上がるのは、
風に向かっている時である。
風に流されている時ではない。“
” 決して屈するな。
決して、決して、決して!“
と言って庶民の
ココロを打ちました。
これらの主導者たちは、
それぞれの時代や
状況の中で、
言葉の力を
最大限に活用し、
人々の心を動かし、
歴史を動かす
原動力となりました。
他人の行動を
変容させる言葉は、
小難しい論理や
理性ではなく、
究極の恐怖心を
煽るものでもなく、
ただただシンプルで力強く、
暑苦しいほどの
素の思いが大衆の
情動に働きかけるんだと
思います。
