
皆さん、
今まで生きてきた中で
様々な組織、
様々なルールに
適応してきたと思います。
一番初めは家族で、
両親が持っている
価値観・生活習慣を
身につけていきますよね。
ココロの世界では、
幼少期に
養育者(主に親)との間で
身につけた
価値観・考え方を
ビリーフ(信条)と
呼んでいて、
一旦、
このビリーフを身につけると、
死ぬまで変わらない、
ということを言い表した
ことわざが
“三つ子の魂百まで”
と表現されています。
人間が生まれて、
“家族という枠”の中で
生き抜いていくために、
養育者(主に親)が
大切にしているルールを
身につけていきますよね。
躾(しつけ)と
呼ばれるもので、
それを身につけさせるために、
時に養育者は
こどもを怖がらせてまでも
ルールを
身につけさせようとします。

その後、
こどもが進学して、
学校に通い始めると、
学校にも校則という
ルールがあります。
人間、
この“学校という枠”でも
ルールにも適応して、
生き抜こうとします。
少数派として、
“不良”と呼ばれる
人達がいて、
異端とみなされて
ルールを破った人には
見せしめとして、
罰則(謹慎、体罰、
停学、退学など)が
課せられ、
この罰則を受ける光景が
強迫を煽って、
その他の属している人が
より何も考えずに、
“従っていれば、
怖い思いはしない”
という思い込みを持って、
本意でなかったとしても
そのルール縛り、
“学校という枠”に
適応していきます。
この図式は
クラブ活動をやっても、
変わらないですし、
学校を卒業した後に
就職して、
今度は
“会社という枠”
の中にいる時も
全く同じ図式です。

それで、
“組織に属することが嫌だ”
とか、
“〇×△という枠の中で
縛られるのは、大嫌い”
という方は
会社に就職せずに、
大学在学中に
ご自身で起業したり、
大学卒業と共に
起業したりする人も
いますよね。
でも、幼少期に
身につけた他人と
人間関係を
気付く上でのルール
や
“公序良俗の枠”
“一般常識の枠”、
業界や社会に
流れている同調圧力に
よってできる
“ある枠”
に閉じ込められていることに
気付いていますか?
上述で確認して頂いた通り、
人間は生まれてから
様々な枠の中で、
生き抜いた結果として、
様々なルールを守ることに
適応しています。
これが国際社会から
日本が評価される、
“協調性”とか、
“規律性”の
基になる気質です。
この気質と
ある意味逆にあるのが、
“新規性”
や
“独創性”と
呼ばれる気質です。
平たい言葉で言えば、
“ゼロから何かを
作り出す”
もしくは、
“既存の何かと何かを
掛け合わせで、
今までにないものを
作り出す”
という気質です。
職業で言えば、
デザイナー、クリエイター、
画家、漫画家、
など文字通り、
創造性を使って、
何かを生み出すことを
生業にすることです。
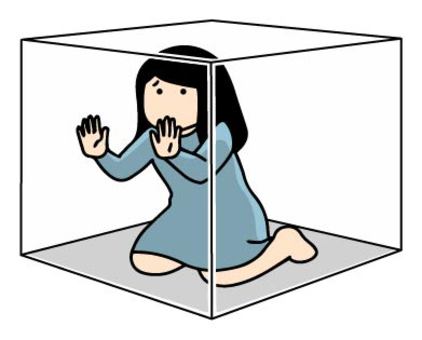
これだけ
高度な情報伝達技術が
発展していて、
ノートパソコン1台あれば
世界中どこからでも
ネットに繋がることが出来て、
誰にでもチャンスがある
時代になってきた
今、世界を相手に
存在価値を示せるのは、
“協調性”や“規律性”
ではなく、
“新規性”や“独創性”
であるといえます。
では、その
“新規性”や“独創性”を
習得するためには、
どうすればいいのか、
という疑問が湧いてくると
思います。
概していえば、
“その枠”
の外に出ることです。
生まれてから長い時間を
かけて作ってしまった
“一般的には・・・”
とか、
“ふつうは・・・”
とか、
“常識では・・・”
の外側に出ることです。
実際に、
物事には必ず
良い面
と
悪い面
があります。
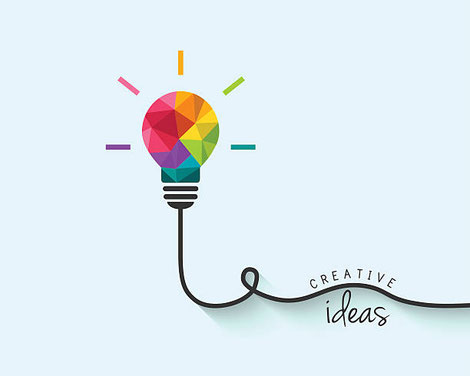
上述でいう“その枠”の中に
いるためには、
“良い面”しか見ていない、
もしくは
“悪い面”しか見ていない、
ことがほとんどです。
必ず両面
(良い面、悪い面)が
ありますので、
そこに意識を向けることです。
自分自身の中にある
正義の価値判断基準に
従ってしまうと、
必ず、“その枠”の中に
入ってしまいます。
ですので、
いつもは嫌いでみてこなかった
側面を凝視してみて下さい。
いつもは意味ないと
思ってスルーしていたことに
注目してみて下さい。
自分自身の中に
ある価値判断こそが
“その枠”で、
それがあることで
“新規性”や“独創性”を
失ってしまっているなら、
その価値判断基準を
緩めてみることが
まずは大切ですね。
